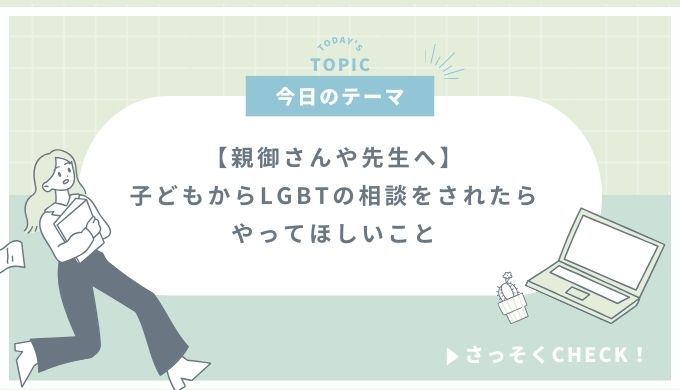性的マイノリティの子どもたちから相談を受けた際、ぜひ思い出していただきたい「3つのステップ」と「2つの”ナイ”」をご紹介します。
「3つのステップ」
①聴く
初めて人に話すという子どもも少なくないため、人がいない場所に移動するなど、安心して話せる環境づくりを意識してください。また。「話してくれてありがとう」と伝えるなど、その子が今後も安心して相談できるような声かけをしてください。
②知る
個々人で困っていることや、求めていない対応は違いますので、その子自身がどうして伝えてくれたのか。何に困っているのかということを聞いてください。また、人によっては、何か対応を求めているのではなくて、自分のことを知ってほしいなという気持ちでカミングアウトする場合もあります。
③繋げる
子ども自身が情報を知ったり、交流するために、多様な性についての本や、電話相談、自助団体などを必要に応じて伝えてください。また、相談を受けた人も相談者も匿名性を名乗りながら、相談期間へ相談することも躊躇わないでください。
【よりそいホットライン】
(24時間無料電話相談)
0120-279-338
(4番:セクシュアルマイノリティ専門回線)
「2つの”ナイ”」
①「決めつけない」
セクシュアリティはアイデンティティだからこそ、本人しか決められません。だからこそ、「思い過ごしだ」「そのうち治る」「きっとゲイに違いない」などその子どものセクシュアリティを否定したり、決定を促したりしないでください。セクシュアリティは迷ったり、決めないでいたり、いつ変わったりしてもいいのです。無理にあてはめようとせず、その子のまま受け止めてください。
②「広めない(共有しない)」
他の人に勝手に情報が伝わると家庭や学校での居場所がなくなってしまう可能性もあります。そのため、本人の同意なく第三者に伝えることは避けてください。共有する必要がある際には、本人に確認の上、進めてください。
LGBTQの子どもの為に今日からできること
相談を受けた時の対応も非常に大事ですが、「この人に相談できる」と思える大人が身近にいることや、日頃から多様な性を意識し子どもの相談しやすい環境を作ってくださる大人がいることも大切です。そのために今日からできることを考えてみました。
- セクシャルマイノリティのニュースや話題を日常的に取り上げ、子どもたちに肯定的に伝える
- 「男なんだから〇〇」「女なんだから〇〇」という言い方や見方はせず、子としてのその子を見る
- 「いつかは結婚するんだから」「親になったら」など、みんなが結婚や子育てをすることを前提とせず、人生設計は多様でいいことを伝える
- 「彼氏/彼女」ではなく「パートナー」など、性別を限定しない言葉を使う
- 性的マイノリティが話題のネタにされていたら、他の人権課題と同様に注意する
- セクシャルマイノリティに関する本や資料などを家、図書館、学校の保健室・図書室。教室などに置く
- 6色のレインボーアイテムを身に付けたり、置いたりする。
※赤・橙・黄・緑・青・紫の6色の虹はセクシャルマイノリティに理解があることの国際的な象徴とされています。
教職員の場合
- 学級通信や保険だよりなどで、セクシャルマイノリティについて書く
- 授業でセクシャルマイノリティや多様な性について取り上げる
- 教職員や保護者が多様な性について知る機会を作る
 ともよせかなとの忘備録
ともよせかなとの忘備録